
大学受験生が抱える悩みの1つに「参考書や問題集の選び方・使い方が分からない」というものがあります。
特に数学の場合、志望校によってレベルや分野がある程度定まってくるため、それらを正確に把握した上で最適な参考書や問題集を選ぶことが重要です。
そこで今回は、大学受験の数学について参考書・問題集の選び方・使い方をご紹介します。
偏差値40台から目指す
早慶GMARCH講座
など、難関私大に合格するための考え方・テクニックをお伝えします。下記より無料でご登録下さい。
まず、大学受験の数学対策に有効な「参考書」の選び方を、3つのポイントにまとめました。
大学受験の数学対策では、まず「基本の1冊」を決めるところから始まります。
・高校数学の内容を一通り押さえた参考書
・基礎力を養うことを目的とした参考書
上記の観点から、現時点の学力レベルに合わせて選ぶのがおすすめです。
書かれた内容が「分かる」参考書と「ちょっと難しい」参考書なら、「分かる」ほうを選びます。
なぜかというと、数学は基本ができていないといくら応用を習得しようとしても身につけることが困難だからです。
まずは基本の1冊を進め、2冊目、3冊目の参考書に取り組んでください。
2冊目以降は、苦手分野を克服するための参考書を選びます。
「基本の一冊」を進めていく中で、徐々に得意分野や苦手分野が明らかになってくるはずです。
苦手分野を克服するために、単元別の参考書を選びましょう。
苦手分野をなくすことで、基礎力の底上げになります。
応用(演習型)の参考書に取り組むのは、数学の基礎力が確実に身についてからにします。
数学は【1】でもお伝えした通り、基本ができていないと応用を身につけることは困難です。
十分な基礎力が身についていない状態で応用の参考書に取り組んでも、その内容を半分も理解することはできないでしょう。
理解しようのないものに時間をひたすら費やすのは効率的ではなく、場合によっては自信をなくしてしまう可能性もあるのです。
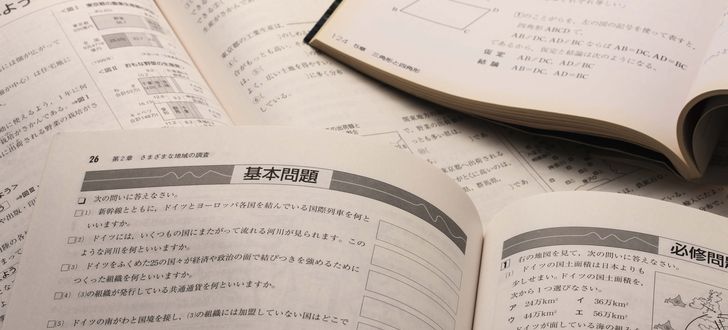
大学受験の数学対策では、参考書で解法を押さえつつ、実際に問題を解くことも欠かせません。
続いて「参考書」の選び方を2つのポイントにまとめてご紹介します。
難関大を志望しているからといって、いきなり難易度の高い問題集を選んでしまうと、難しさに意欲が低下してしまう可能性も。
まずは基礎をしっかり身につけ次に標準的な問題に取り組み、難易度が高い発展形の問題にはその後から取り組むことをおすすめします。
数学の入試問題は、計算過程を示す記述式が出題されることもあります。
限られた時間内で採点者に分かるよう計算過程を書けるか否かは、日頃からの丁寧な考察と演習に懸かっています。
解説(問題を解く際の着眼点)が丁寧で、解答の組み立て方がしっかり説明されている問題集を選びましょう。
必ずどのように解答が組み立てられているか、解説を確認します。
解けなかった問題はもちろん、解けた問題でも必ず実施してください。
こうすることで入試本番でも計算過程を適切に書き残せる力が身につくのです。

ここまで紹介した内容を元に参考書・問題集を選んだら、あとは実行あるのみ。
おすすめの参考書・問題集の使い方を3ステップでご紹介します。
まずは教科書で入試対策の準備をします。
学校の予習・復習がそのまま大学入試対策の第一歩となるため、毎日の自宅学習は疎かにできません。
授業を受けて解消できなかった疑問や解答に時間がかかった問題をチェックし、何を対策せねばならないのかを洗い出してから参考書や問題集へ進みます。
1冊目の基本の参考書・問題集で、書かれた内容はすべて覚えられるくらい頭に入れられるよう取り組みましょう。
基本問題では「インプットする意識」が大切です。
基礎が身についたら、演習型の問題集で「アウトプットの意識」を高めます。
基礎の参考書や問題集で身につけた知識に基づいて応用力をつけ、さまざまなスタイルの問題を解答できるようにします。
この段階で志望校の過去問にも取り組みます。
受験する大学の出題傾向をつかんでおくことは重要です。
今回は、大学受験の数学で必要な参考書と問題集の選び方・使い方のポイントをご紹介しました。
私立大学の数学では、大学ごとに出題傾向があります。
私大受験専門のプロ家庭教師「メガスタ」はそれを踏まえ、「出題傾向を押さえた志望校対策」に力を入れています。
どこにお住まいでも、最新の受験情報に基づいた指導を受けることができます。
学校の授業についていけない受験生はもちろん、予備校だけでは物足りない受験生も、ぜひ「メガスタ」の活用をご検討ください。
基礎から実践まで、受験生個々のレベルを見極めた最適な指導を提供します。
偏差値40台から目指す
早慶GMARCH講座
など、難関私大に合格するための考え方・テクニックをお伝えします。下記より無料でご登録下さい。